ラーメン生誕100年 発祥は横浜
院長の父親である大先生・浜野文夫が約30年にわたって全国各地の「味の旅」13巻のアーカイブ集です。
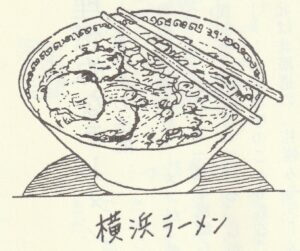
開港と共に文明開化がやってきた。「モノ皆、横浜カラ始マル」と言われるが、ラーメンも横浜から生まれたと考えられる。 明治四十年代前半、唐人街(中華街)の小さな広東料理の屋台から生まれたラーメンは、豚骨の白濁した塩味のスープで「南京ソバ」と言っていた。そして今年、生誕一〇〇周年を迎える。ただ、ラーメン発祥の地には諸説がある。横浜説は明治時代に塩味のメンがあったと紹介されており、長崎など各地の居留地にも中国のメン料理はあっただろうが、長崎はチャンポンとして発達した。横浜には明治時代に中華料理店があり、今日までメンマの入ったラーメンとして続いており、横浜が発祥と推測される。
一方、『横浜もののはじめ考』という本を出している横浜開港資料館は「外国人居留地があった状況から横浜から生まれたとしてもおかしくないが、何をもってラーメンというのかが特定できず、史実としてはわからない」という見方だ。やがて関東風の醤油味となって東京方面に進出し「支那ソバ」として徐々に広まってゆき、大正年間から昭和の初期には、屋台の支那ソバは、チャルメラの響きと共に懐かしい光景があった。
戦後は、〝そば〟といえばラーメンを指して、もり、かけのたぐいは「日本そば」と言うようになった。ラーメンという呼び名は戦前からあったが、たいてい支那ソバ、中華ソバと言った。今や国民食と化したラーメンであるが、その変容ぶりは、多種、多彩である。ラーメンの上に塩焼きのサンマや、塩サケを乗せたり、毛ガニ一匹が丸々乗っかるものまで登場する。 そして、いわゆる本家、本元、元祖横浜ラーメンはいまも健在か、といえば、最近はラーメンブームも定着し、多様な食べ物が豊富でラーメンを追っかける人も少なくなったが、まず中華街を避けて探すことだ。
中華街のメンはラーメンとは異質のもので、ラーメンじゃない。伊勢佐木町とか野毛近辺の裏街に、小さな店で、カウンターに座ると、目の前に鉄の大鍋が二ないし三、鎮座し、中でブタの耳、足、頭などがグツグツ音を立てている。という店は昔の話。今は豚骨が煮えたぎっている。〝とんこつラーメン〟が主体だ。
ラーメンが「支那ソバ」と呼ばれていた頃から、正統派のものには決まった具がある。ナルト、メンマ、チャーシュー、ホーレン草、海苔である。そのどれ一つ欠けてもラーメンにならない。皆それぞれメンを食べるための箸やすめの、脇役としての意味がある。最近、変型が多くて良くない。 ラーメンは、タレとスープとメンが、丼の中で一体化し一つの味を作りだす、世界で類をみない不思議な料理である。
一、オードブル(メンマ、ナルト)二、スープ 三、メインディッシュ(チャーシュー)
四、サラダ(ネギ、ホウレン草、モヤシ)五、そしてパン又はライスの代わりにメン。
これを一つの丼の中に集めると、まさにフランス料理のフルコースに匹敵する。
ラーメンで一番たいせつなのは、醤油味のするタレとスープである。たいていはその店の秘伝である。最近ラーメンはツユが臭い。材料に原因がありそうだ。次回は「理想的なラーメン」と「食べ方の法則」を指南することにしよう。今回は生誕100年にこだわった。生誕100年というのは、明治42年生まれのことである。今年、生誕一〇〇年の作家には松本清張、太宰 治、中島 敦がいる。俳優では上原 謙、田中絹代だ。中島 敦(33歳没)は、横浜ゆかりの作家で、今も自筆稿には熱烈なファンが多い。横浜が生んだ異色の作家であり、ふと彼のことを思った。
(平成二十一年三月)
図中のイラストは大先生本人の描写です
はまの歯科医院:https://www.hamanodc.com/
〒232-0024 横浜市南区浦舟町4-47-2 メディカルコートマリス202
電話:045-251-4181
電車でお越しの方:
横浜市営地下鉄「阪東橋」駅下車 徒歩5分
京浜急行「黄金町」下車 徒歩10分
横浜市営バス「浦舟町」下車 徒歩1分

